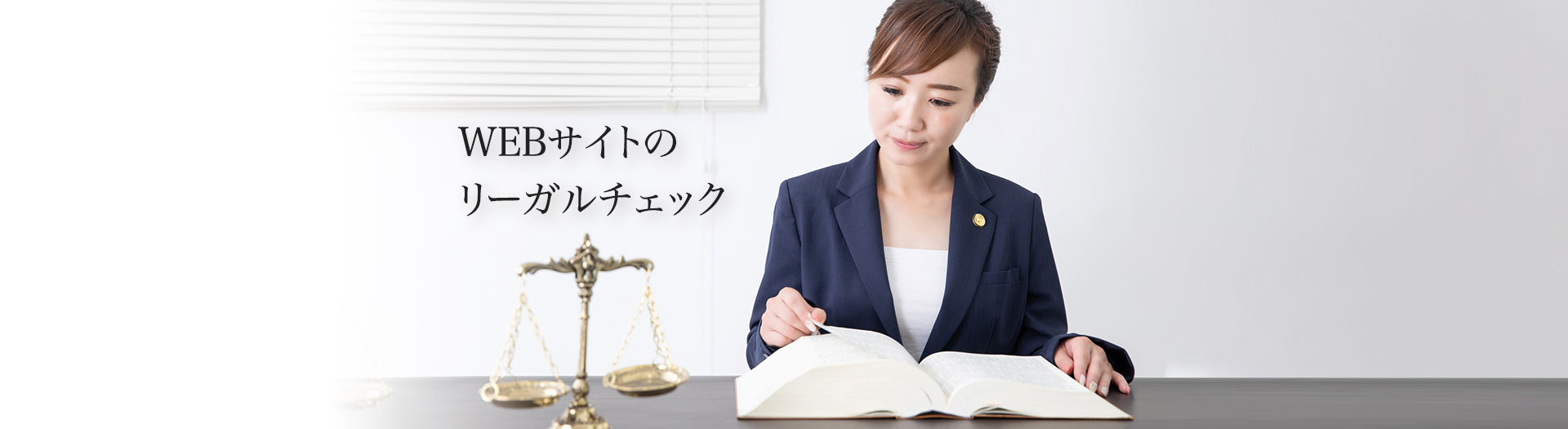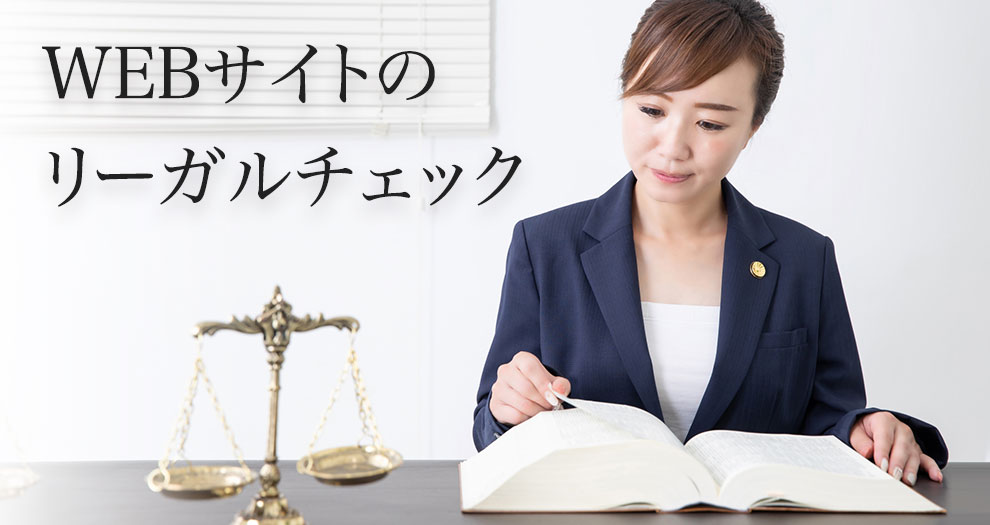現代社会では、多くの人がインターネットを使って利用する商品やサービスを検索します。
自社のコーポレートサイトがないと、信用を得にくくなるでしょう。また販促のためにオウンドメディアを構築する企業も増えています。
ただしWebサイトの広告表現には多数の法規制が及ぶので、正しい法知識をもってサイト運営を進めましょう。
自己判断でサイトを公開すると知らない間に「違法行為」となってしまうリスクも発生します。Webサイトの構築や運営の際には、ぜひ弁護士によるリーガルチェックをご利用ください。
IT法務全般・ソフトウェア・著作権 ブログ
-
当事務所所属弁護士が執筆したビットトレントの裁判例に関する研究ノートが掲載されました
-
当事務所弁護士のビットトレントに関する論文が掲載されています
-

ビットトレントで発信者情報開示請求を受けた方への情報
-

フィッシングメールをきっかけに考える,自己の情報に関するオープンクローズ戦略
-

ウェブサイトにフリー素材写真を掲載する際に気を付けたいこと
-
Google LLCに対する仮処分の際の資格証明書の取扱いについて(代表者が登記された件)
-
理系弁護士が匿名掲示板の発信者情報開示請求スレ(BitTorrent系)を見て思ったこと(1)
-
当所での簡単なオンライン相談のやり方
-
知財高裁の裁判例令和3年(ネ)第10074号から考えるbittorrentによる著作権侵害についての侵害者側の...
-

事業をする際に知っておきたい商号と商標の基本クイズ
-
BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトウェアで発信者情報開示請求を受けてしまった場合のゴ...
-

中小企業の経営者がすべき情報セキュリティ対策について〜IPAセキュリティセンターのガイドラインより〜
-

エルデンリングのプレイ動画配信禁止騒動で考える、著作権の事業活用について
-
BitTorrent(ビットトレント)系のP2Pソフトウェアによる著作権侵害について
-

誤解しているかもしれない著作権の基本クイズ(2)
-

契約の電子化(オンライン化)についてよくある質問
-

SNSにおける民事/刑事の名誉毀損と、侮辱罪の厳罰化について
-
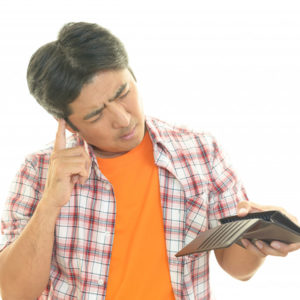
誤解しているかもしれない著作権の基本クイズ(1)
-

著作権の話と契約の話を区別することの重要性〜オープンソースソフトウェア(OSS)を例に〜
-

著作権問題の全体像(後編:権利の侵害)
-

著作権問題の全体像(前編:権利の帰属)
-

企業視点で見た産学連携の注意点<後編>
-

企業視点で見た産学連携の注意点<前編>
-

権利侵害の警告状を受けたら最初に確認すること(著作権編)
-

他社に権利侵害の警告をする際の留意点(特許編)その2
-

社内の業務ロジックをブラックボックスにしてはいけない理由と、顧問弁護士の活用のすすめ
-

他社に権利侵害の警告をする際の留意点(特許編)その1
-

料金が安い事務所に頼むのが「お得」?
-

弁護士と司法書士の違い
自社コーポレートサイトの適法性チェック
今の時代、特にインターネットマーケティングに力を入れていなくても自社サイトは持っている、という企業が多数です。
現在はホームページがないけれどこれから作成したい、という企業もあるでしょう。
自社サイトを作るときには、以下のような点に注意してください。
- 利用規約
-
サイトから直接集客する場合、利用者との間で適用される利用規約を定める必要があります。利用者との間でトラブルが発生しないように、サービス内容に応じた適切な規約を作成しましょう。また2020年4月1日からは民法改正によって「定型約款」という制度が適用されるケースもあり、規約作成には法的な知識が必要です。
- プライバシーポリシー
-
個人情報を取り扱う企業は、サイト上にプライバシーポリシーを定めておくべきです。どういった目的で個人情報を収集するのか、情報管理方法や個人情報の開示請求、訂正請求方法など明らかにしましょう。
- 広告表現の適法性
-
自社サイトでは、何らかの広告表現を行うケースが多数です。広告には法律規制が及ぶので、キャッチフレーズなどを掲載するときには正しい知識が要求されます。知らず知らずのうちに「景品表示法」や「薬機法」などの法律に違反してしまったら、高額な課徴金を課されたり罰則を適用されたりする可能性もあるので注意しましょう。
- 特定商取引法に基づく表示
-
特定商取引法の適用対象となる企業では、特定商取引法によって一定事項の表示を義務づけられ、誇大広告も禁止されます。違反すると業務停止命令を受けたり罰則が適用されたりするおそれがあるので、注意してください。
弁護士にご依頼いただけましたら御社のコーポレートサイトに法的なリスクがないかチェックいたします。安全にサイト運営を進めるため、是非とも一度ご相談ください。
自社オウンドメディアの適法性チェック
最近では、自社で集客に特化したオウンドメディアを運営する企業も増えています。商品の専用販売サイト、サービスを宣伝するためのサイトなど、ブログ記事を多用しながらマーケティングする戦略も人気を集めています。
これらのオウンドメディアでは、コーポレートサイト以上に「適法性」に注意が必要です。上記で紹介した「特定商取引法にもとづく表示」などの他、以下のような点にも注意しましょう。
- 著作権
-
オウンドメディアを構築する際には、記事や写真、イラストなどを外注するケースが多数です。その場合、それらの著作物の著作者から「著作権」の譲渡を受けておく必要があります。著作権が著作者に残ったままにしていると、後に著作者から権利を主張されてトラブルになるリスクが発生します。
- 商標権
-
自社サイトに他社が権利取得している商標を使ってはなりません。完全に同じでなく「類似している商標」であっても利用を制限されます。また商標登録されていなくても、「不正競争防止法」により、混同を招くような表示は禁止されます。他社を想起させるようなドメイン取得まで制限されるので、注意しましょう。
- 肖像権やプライバシー権
-
他人が写り込んでいる画像や動画を使うと「肖像権侵害」となります。また他人の個人情報がわかるような記載をするとプライバシー権侵害となってしまう可能性もあります。
オウンドメディア運営の際には権利侵害をしないよう十分配慮が必要です。 - 名誉毀損
-
ブログ記事などに他社や他人の名誉権を侵害する内容が含まれていると、名誉毀損として訴えられてしまう可能性があります。特に他社商品やサービスと比較する際には注意しましょう。ライバル社の実名を出さない場合でも、「知っている人が見たらどの会社のことを言っているのかわかる場合」には名誉毀損になる可能性があります。
- 薬機法
-
健康食品や美容関係のオウンドメディアを構築する際には薬機法(旧薬事法)に注意が必要です。医薬品でない商品によって「治る」など状態が改善するような表記をしてはなりません。ビフォーアフターの写真比較や口コミも規制対象になります。
オウンドメディアを運営するときには、法律に詳しい専門家によるサポートが必須となるでしょう。これからメディアを後悔しようとされている方、すでに運営しているサイトに不安がある方は、弁護士までご相談ください。
広告の法律
Web広告には、以下のような法律が適用されます。
- 景品表示法
-
景品表示法は、web広告でマーケティングを行うときにほとんど必ず適用される重要な法律です。基本的に「消費者に誤認させる表示」が禁止されます。虚偽の表示、実際より優良と誤認させる表示は禁止されますし、「期間限定」と表示して購買意欲をあおる場合や「もともとの価額と特別に適用される価額」の二重価格表示も規制対象です。
- 特定商取引法
-
エステや英会話などの継続的なサービスを提供するビジネス、ネット通販などには特定商取引法が適用されます。特定商取引法にもとづく表記として、販売価格や代金支払時期、事業者の名称、場所、電話番号や責任者の氏名など、一定事項について必ず表記しなければなりません。ネット通販の場合には「返品特約」についても記載しておくべきです。
- 薬機法
-
薬機法は、医薬品や医薬部外品、化粧品や健康食品などに関する広告表現を規制する法律です。これらの商品について間違った広告が行われると、信じて購入した消費者の健康に重大な影響が及ぶ可能性があるため、非常に厳しく規制されます。特に近年では制限が強化されて細かいガイドラインも作られているため、正しい知識を持った対応が要求されます。
- 不正競争防止法
-
企業間の公正な競争を維持して市場の健全な運営と発展を目指す法律です。他社の商品やサービス名を勝手に利用したり混同させるような表現をしたり、商品を模倣したり営業秘密を不正取得・利用したりする行為などが禁止されます。
- 商標法、著作権法
-
商標法は、登録された商標を保護するための法律、著作権は著作物と著作者を保護するための法律です。商標登録された標章を勝手に利用すると損害賠償請求されるおそれがありますし、罰則も適用されます。
ネット上の文章や画像などの著作物を勝手に転載すると、著作権侵害となって著作者から損害賠償請求や差し止め請求を受ける可能性があります。
サイト上での広告を規制する法律では、法改正も頻繁に行われています。自社のみで完璧に対応するのは難しいでしょう。お気軽に弁護士までご相談ください。
ネット通販で注意すべき法律
ネット通販業を営むなら、最低限以下の2つの法律には注意が必要です。
- 特定商取引法
-
通信販売業には特定商取引法が適用されるので、サイト上に「特定商取引法にもとづく表示」が必要です。
誇大広告が禁止されますし、承諾していない人に対して広告メールを送ってはならない規制もあります。メール配信する際には、後に「拒否しているのにメールが届いた」といわれないため、消費者による承諾の経緯を残しましょう。
またネット通販にはクーリングオフが適用されませんが、返品特約を表示していない限り商品を受け取ってから8日以内の返品が可能となります。
返品特約を表示する場合「サイト内の明瞭に分かる場所」と「最終確認画面」の2つに特約を表示しなければなりません。こうした規制を理解してサイトを構築しましょう。
- 景品表示法
-
景品表示法では「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が禁止されます。
優良誤認表示とは、実際よりも著しく優良に見せる広告です。たとえば産地偽装、使用している材料についての虚偽などが該当します。
有利誤認表示とは、実際よりも取引が有利になると誤認させる広告です。たとえば「期間限定で50%引き」と表示しつつ、実際には30日が経てば期間を延長してずっと50%引きの価格を提供している場合などです。
上記の他にも個人情報保護法や薬機法などの法律に配慮が必要なケースも多々あります。
ネット通販を行う際には必ず弁護士によるリーガルチェックを受けましょう。
著作権の保護
Webサイトでは「著作権侵害」が起こりやすいので注意が必要です。重要なことは以下の3つです。
- 他サイトの記事や写真、イラストなどの著作物を転載しない
-
他サイトに掲載されている記事や写真、イラストなどの著作物を転載すると著作権法違反となります。必ず著作権フリーの素材か買い取った素材を利用しましょう。
- 外注するときには必ず著作権の譲渡を受ける
-
記事や写真、イラストなどを外注するときには、必ず著作者から著作権の譲渡を受けましょう。契約書を作成し、著作権の譲渡を明確にしておくべきです。
- 自社の著作物が転載されていたら差し止めや損害賠償請求を検討する
-
サイトを運営していると、自社の記事や写真などが無断転載されて著作権侵害の「被害者」となる可能性もあります。他サイトに自社が掲載した写真や動画、イラスト、記事などが勝手に転載されていたら、差し止め請求や損害賠償請求を行いましょう。
弁護士がついていれば著作権侵害をしていないかチェックできますし、侵害されたら相手方に対する各種請求が可能です。お悩みの際にはぜひご相談ください。